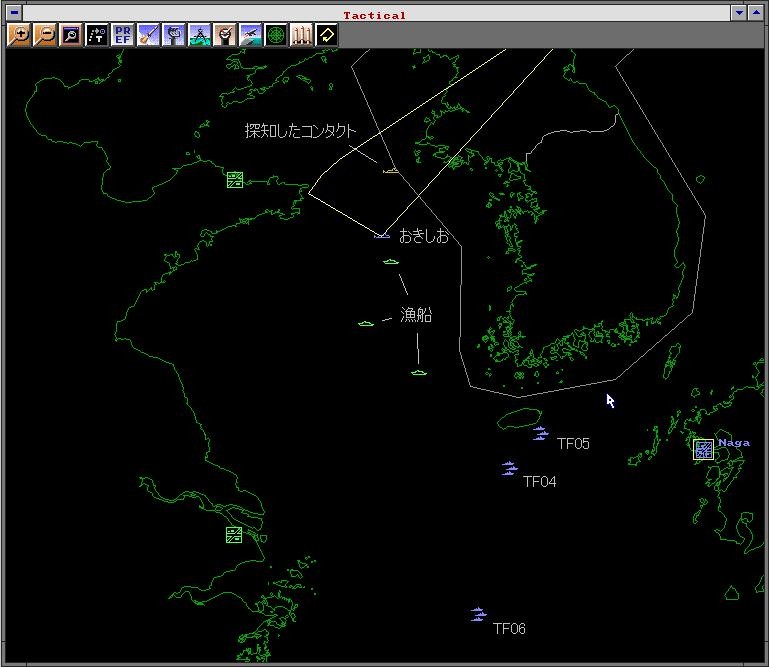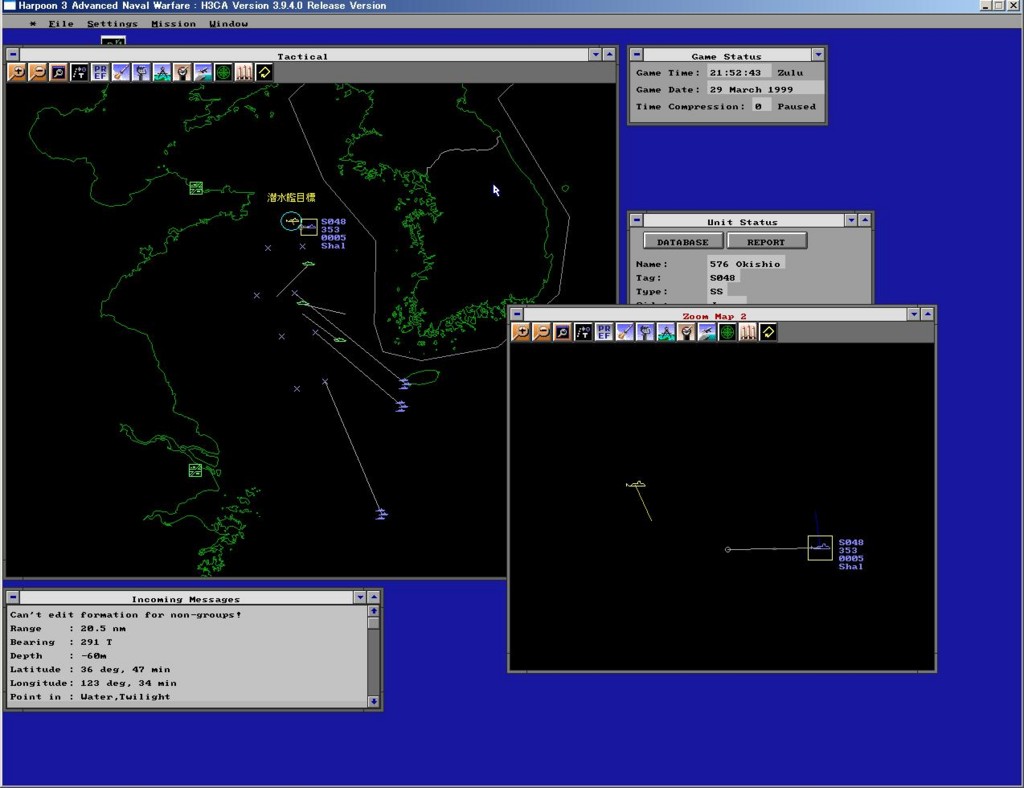先日スチムーでセールだったので購入した。これが予想外に当たりで、定価の$10でもよかった、というレベル。いやあ、存在は以前から知ってはいたのだが、RTSだとばかり思っていたので手を出していなかったのね。個人的にRTSは無理レベルで苦手なので…
公式サイトはこちら。購入するなら公式経由をお勧めする。
で、じゃあどんなゲームかというと、一言で説明するのは難しい。開発元は「FTL is a spaceship simulation roguelike-like.」と言っていて、確かにローグライクな薫りはほのかに漂っている。ローグライク、といっても*bandではなくnethackな感じ。一応、「反乱軍に押されている戦況のなか、趨勢を逆転させる重要な情報を入手した艦を、追手にやられないように自陣営まで帰還させる」的なストーリーは存在してはいるがまあフレーバーテキストの域を出ない。
ゲーム自体はいたってシンプル、
- 現在の星系に隣接する星系にジャンプする
- ジャンプ先でさまざまなイベントが発生する。敵艦がいれば戦闘だし、ショップがあれば収集したスクラップと引き換えに各種装備の売買や補給、修理、クルーの雇用などができる。
- 現セクターの出口となる星系まで辿りつけば、次のセクターへジャンプできる。
- これを繰り返して自陣営に戻り、反乱軍の旗艦を迎え撃ち破壊すればよい。
これだけである。
画面にはつねに自艦の平面図が表示されていて、兵装、エンジンといった各種システムが配置されている。レイアウトは選択した艦種ごとに違っている(同型艦でも2パターンあり、アンロック後選択できるようになる)。また、乗員の位置も表示されている。
宇宙モノといえば、コックピット視点のシミュレーターのようなものを連想しがちだが、このゲームは自艦を自分で動かして戦闘する類のものではない。戦闘でプレイヤーが行う操作は、概ね兵装の選択と発射タイミングだけである。自艦や敵艦内での白兵戦や、故障箇所の修理、火災への対応についてはRTS的な要素がないわけではないが、このゲーム、いつでもポーズできるためプレイヤーの操作テクニックが要求される場面はない、といっていい。むしろボードゲーム的な雰囲気が色濃いゲームといえる。
これだけシンプルだと飽きも早そうだが、これが意外と長く(すくなくとも定価の$10分は十分に)遊べるゲームになっている。それに貢献しているのが、開発者も言っている「roguelike-like」なところだ。
このゲーム、難易度がかなり高い。一応easyとnormalがあるのだが、プレイに慣れないうちはeasyですら最初のセクターで死ぬことが珍しくない。また、ラスボスがこれまた強く、それなりにプレイに慣れたプレイヤーにとっても高い壁となる。おれもまだこれ倒せてないんだようん…しかし、1回のプレイ時間が比較的短い(ラスボスまでいっても~2時間程度)ので、何度もプレイを繰り返しながらプレイヤー自身の経験値を上げていくという楽しみ方ができる。最初は各種装備の使い方や特性すらわからずに途方に暮れるのだが、そのうち「ああ、こう使うのか」と理解していく感覚。このあたり、spoilerなしでプレイするnethackに近いといえば近い。
また、ランダム性が強いのも基本的にはポジティブに働いている。このゲームには色々な兵装や装備が存在し、それぞれ特色がある。つまり、何を装備しているかで戦闘方針がまるで変わってくるのだが、どの装備を入手できるかは運に左右される。店売りのものであればある程度選択肢があるが「3種類から好きなものを選ぶ」というものであり、プレイのたびに同じ装備を揃え同じ戦術を取る、というわけにはいかない。よって、入手できた装備に合わせた戦い方をすることが要求されるし、場合によってはろくに装備を揃えられずキツい状況に陥ることもある。早い段階でteleporter(敵艦に乗員を送り込める)を手に入れたはいいが、肝心の乗り込み要員が一向に集まらないだとか、beam兵器(複数区画を横断してダメージを与えられるがシールドには基本無力)はあるのにシールドを破る手段が貧弱で使えないとか…
そんなわけで、とっとと買っておけばよかったと後悔しつつ楽しんでいるところである。こんなテキストじゃ面白さはおろか、どんなゲームかも伝えられないのが残念だが、ニコ動やYouTubeにプレイ動画があるので興味があればそちらを参考に。もし、これからプレイしようという方がいたら、まずwiki(英語のは存在するようだ)や2ちゃんねるの当該スレッドは見ずに遊ぶことをお勧めしたい。この手のゲームは、手探りで色々理解していく過程が何より楽しいので。